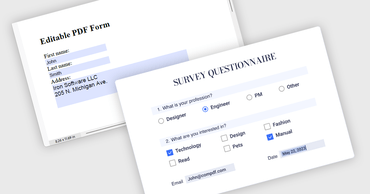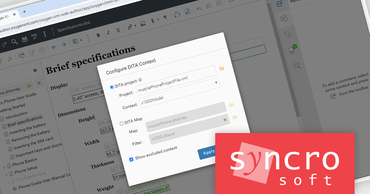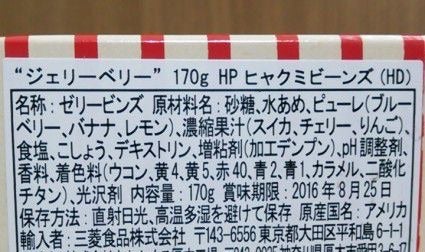ウェブ魚拓より 世界医薬産業の犯罪
PART6 無用の惨劇●動物たちの復讐『罪なきものの虐殺』への追補●レイプ・ラック●代替法『罪なきものの虐殺』への追補●堕ちた偶像『罪なきものの虐殺』への追補●心臓だけではなく肺も●そして骨髄も●そして狂気へ●ついに脳の移植
ーーーーーーーーーーーー以下転載ーーーーーーーー
PART6 無用の惨劇
イギリスの女医第一号、アナ・キングスフォード博士は次のように書いている。
「動物実験者の魂に巣食う精神の堕落は、彼から最高最善の知識を得る能力を奪う。
彼は健康の秘密を発見するよりは、病気を蔓延させることの方がはるかに容易だということを知るだろう。
彼は生命を蝕む細菌を探し求めるが、見出すのはただ新しい死に方のみである」。
***
科学は人類に迷信からの救済を約束した。
しかし、自らが歴史上、もっとも高慢で残虐な迷信と化した。
これは現代文明の生んだ最大の悲劇と言えよう――かつて、もっとも秀れた常識のフォルムであった科学は、今や神として生まれ変わった。
民衆(信徒)も科学者(司祭)とともに天上の声を聴く科学はかく仰せられる、かく求めておられる、と。
科学は機械的な神である――かつての神々は司祭に去勢を求めた。
しかし科学は司祭に、人間的感情を取り除くよう要求する(ブリジツド・ブロフイ『ザ・リスナ~』一九六九年)。
***
人の寿命は少しも変わっていない。
人は老いると病気がちになる。
どんなに多量の薬を飲もうと、どんな手当をしようと、六五歳という平均寿命は、この一世紀の間ほとんど変化していない。
薬は老化に伴う疫病には手の出しようがない。
老化現象そのものにはさらに手の出しようがない。
薬は
心臓病も癌も関節炎も肝硬変も、そしてごく普通の感冒さえも治せない。
確かに老いた人々の苦痛の一部は緩和できるようになった。
しかし残念ながら、一般論としては、老人への専門的医療措置は苦痛を増加させる。
そればかりでなく、措置がうまくいった場合、かえって苦痛を長引かせる結果になっている(イヴァン・イリッチ『医学のネメシス』p45,"ロンドン、一九七五年)。
***
「多数の労働者に職がない時、失業問題がおこる」というフーバー大統領の有名な論法がある。
実はこれは、学術論文でしばしば見かける論法なのである。
「生体が食物を与えられなければ飢餓がおこる我々はこれを、統計的に有意な数のイヌ、ネコ、サル、ロバ、ブタその他の動物を使って科学的に証明した。
また助成金が与えられれば、これを再度証明する準備がある」
しかし今日、「基礎研究」と呼ばれる仕事に携わる人々は、このような見え透いた言いわけをするだけの良心もなくしてしまったようだ。
「基礎研究」といえば響きは良いが、つまりは、健康な動物にまったく不必要な拷問を加え、肉体的精神的に破壊してしまうという作業のことである。
これは正気な人間にとっては、考えることさえ不可能、ましてや実行することなど論外な行為なのである。
↑
●動物たちの復讐『罪なきものの虐殺』への追補
WHOによれば、肉体的精神的にハンディキャップを負った人の数は、一九八〇年に世界中で四億五〇〇〇万人、すなわち世界人口の約一〇パーセントに上るという。
そのうち一億三六〇〇万人が一五歳以下である。
これは、健康環境が悪化し、かつてないほどに多くの子供たちが、国際教育財団のお節介で、いやがおうでも有害な医療介入を受けている結果の数字と言えよう。
たとえば、胎児期に母胎に施された治療、出生後の各種の予防接種、放射線、合成ビタミンや合成薬品の投与などである。
一億三六〇〇万人の内訳はヨーロッパ一一〇〇万、北米六〇〇万、ラテンアメリカ一三〇〇万、アフリカ一八〇〇万、アジア八八〇〇万となっている。
***
次に引用するのは『臨床薬理学および治療学』(Vol.7,1966,pp.250-270)に載ったイギリスのロバート・シャープ博士の、非常に啓蒙的な論文である。
これは、拙著『罪なきものの虐殺』の内容を確認するものである。
――フレミングはペニシリンが(ペニシリンは偶然に発見された。
動物実験によるものではない――著者)、血液によって不活性化するのではないかと考えていた。
この懸念は、サンプルをウサギに注射したところ、確認されたかのように思われた。
この結果に落胆したフレミングは、ペニシリンをさらに広汎に応用してみようという興味を失い、体表面の感染症に限って使用した。
後にオクスフォードのフローレイとチェインの二人がペニシリンに再注目し、ネズミで感染症に効果があることを確認した。
しかし、ここで幸運だったのが、実験動物の種類の選択である(二人がこの実験を開始した時、彼らの実験室では、もっとも一般的な実験動物であるモルモットが全部死んでいたのである――著者)。
ペニシリンはたとえ微量であってもモルモットには致命的である。
もしネズミの代わりにモルモットが実験に使われていたとすれば、おそらくペニシリンは永遠に日の目を見ることがなかっただろう。
さらに幸運が重なる。
ある重病の患者を救うためにフレミングはペニシリンを脊椎に注射することを考えた。
しかしその結果がどうなるかについては未知である。
フローレイは急ぎネコを使って実験を行なった。
が、その結果を待っていたのでは、フレミングの患者が助かるチャンスはなくなる。
ネコの結果が出る前に、患者はペニシリン注射を受け、回復した。
しかしフローレイのネコの方は死んだ。
この教訓は今もって生かされていないのである。
***
一九八一年四月二十三日、医師、研究者、作家、芸術家などからなる三〇名のイギリス人が、マーガレット・サッチャー首相宛ての嘆願書にサインした。
国の医学研究予算の一部を、動物実験に代わる別の方法の開発専用に回して欲しいという主旨のものだった。
この時も、それまでと同様、サッチャー首相は断固、冷たくNOと言い放った。
同年五月十四日付、ダウニング・ストリートからの返信は次のようなものだった。
「――生化学研究における動物使用に代わる研究方法開発のためにさける国家予算は、残念ながら、ありません。
医学研究委員会は、代替法に関する研究プロジェクトは、従来の研究プログラムの一環として行なうのがベストであると考えています――」。
この「医学研究委員会」なるものが強硬な実験主義者によって構成されているという点はここで指摘するまでもなかろう。
また、「科学畑」出身で、これまでも常に動物実験支持の姿勢を見せていたサッチャー首相は、自身がかつて動物実験に関わっていたのではないかという疑惑を持たれるのである。
事実、動物実験を認めるほどの人は誰でも、実験そのものへの参加をも躊躇しないだろう。
***
西ドイツの保健相アンジ・ヒューヴァーの姿勢もサッチャー首相のそれに非常によく似ている。
一九八一年六月二十五日、ヒューヴァー保健相はボンでの公聴会の席上、動物実験を破棄することはできないし、部分的廃止たとえば化粧品のための実験や残酷な上に間違った結果を導きがちなLD-50(対象動物の五〇パーセントに対する致死量)テストなど――も問題外である、ときっばり言い切った。
ちょうどその頃、保健相の同僚ミルドレッド・シールが、「癌征服プログラム」
のために、マルクをかき集めている最中だった。
ヒューヴァー保健相は、他の仕事があるからと言い二〇分で公聴会から逃げ出した。
あとは保健省の役人の一人が引き継いだ。
この役人は、実験削減の実施すらも難しいと述べた。
というのは、保健省が実験の実態を完全に把握しきれていないためだという。
「たとえば、我々は我が国の大学の中で、何がおこっているのか知りません」と彼女は言う。
また、なぜ保健省がせめて悪評フンプンのLD-50テストだけでも禁止しないのか、と聞かれて、こう答えている。
「もしそんなことをすれば、我が国は薬品を輸出できなくなります」。
この時、彼女は明らかに、アメリカの時代遅れのディレイニイ改正法に言及していたのである。
この改正法は、各種のテストを義務づけたもので、今日の全世界の薬害に大いに責任を負うべき法律なのである。
また、彼女の回答は、サッチャー首相、ヒューヴァー保健相をはじめとする先進工業国の政治家たちが、製薬トラストの利益にいかに深く絡んでいるかを示す証言だったのである。
***
ニューヨーク州ローゼスポイントで発行されているタブロイド誌『ザ・グローブ』の一九八〇年五月二十七日付の記事に次のようなものがあった。
空軍の極秘化学戦・レーザー線研究に携わっていた心理学者が明らかにしたところによれば、殺人光線や電気ショックによってアカゲザルが情容赦なく盲目にされたり苦痛を与えられたりしているという。
テキサス州サン・アントニオのブルクス空軍基地での実験に使われたアカゲザルは、その傷めつけられ方があまりにもひどかったため、自己破壊的になり、自分の腕の肉を噛みちぎったり、胸から毛の塊を抜き取ったりするようになった、と心理学者のドナルド・バーンズは『ザ・グローブ』の単独インタビューに答えて語った。
バーンズはオハイオ州立大学の卒業生で、ブルクス空軍基地で一六年間、研究者として非の打ちどころのない仕事ぶりだった。
しかし、実験用サルの扱いが余りにもひどいため、これを世間に公表すると抗議したところ、今年一月に解雇されたという。
空軍スポークスマン、サルバトーレ・ギアンモは、空軍施設は、実験動物認定協会の検査官による立入検査を、一九七九年五月十五日に受けており、その際、問題なしと判定されたと語っている。
しかし、たとえば首の回りの拘束カラーがきつすぎたため、窒息死した三匹のサルを目撃したとバーンズは語る。
さらにこう証言する。
「椅子に縛りつけられたサルたちが、胸の前でクロスしている金属の棒の間から死にもの狂いで抜け出そうともがいているのも見ました。
サルたちが余りにも激しくもがくので金属棒が腹壁に食い込み始めていました」。
アカゲザルが実験動物として重宝されるのは、穏やかで非常に信頼のおける動物だからである……。
バーンズは言う。
「――台はユラユラ揺れるようになっており、我々はサルたちにその台をまっすぐにするレバーの使い方を教えました。
その訓練の仕方というのは、足の裏に金属板をつけ、
彼らが迅速に正確にレバー操作をしないと、そこに電流が流れるようになっているのです。
なかなか操作を覚えないサルには、突然電気を流してショックを与えて罰しました。
サルは一日に何百回もショックにつぐショックを与えられます――けれども私たちの行なっていた実験はほとんど無意味なものでした。
すでに以前、行なわれたことのある実験ばかりだったんです」。
***
一九七九年九月二十四日付、ロンドンの日刊紙『スター』より。
実験施設へ送られるサルたちは、檻にぎっしり詰め込まれたままの状態で激しく鳴き叫ぶ。
そのため喉が膨れ上がり呼吸ができなくなる。
インドネシアから発送された六二五匹のうち、恐怖の空の旅を耐え抜いて、生きてスウェーデンに着いたのはたった一四〇匹だけだった……。
アムステルダム空港で、サルの輸送風景を目撃したディック・ヴァン・ホーンのコメント。
「九月八日、インドネシア、ジャカルタからスウェーデン、ストックホルムへ送られる数百匹のサル(ジャワ産、アカゲザル)が、乗りつぎのため、アムステルダム空港で数時間待たされていた――取り締まり官が檻のうちふたつを開けるよう命じた。
ひとつの檻には一五匹のアカゲザルが入っていたが、そのほとんどすべてが怪我をしていた。
もうひとつの檻には一一匹いたが、そのうち七匹はすでに死んでいた。
これらのサルの死因は明らかに空気不足で、眼球はとび出し、舌は自分で噛みちぎったものらしかった。
取り締まり官は灯りをかかげて、他の檻も検査したが、次々に死んだサル、怪我をしたサルが発見された――」。
***
国際霊長類保護協会(IPPL)の会長、シャーリー・マクグリ~ル博士のリポートから、サルの輸出に関する情報を少し拾ってみよう。
インド政府は一九七七年、サルが残酷な放射能実験に使われていることに抗議して、輸出禁止に踏み切った。
アメリカとWHOからの強力な圧力、またインド自身の政権交替にもかかわらず、現在も、輸出は再開されていない。
バングラデシュ政府は一九七九年、あるアメリカの業者に七万匹以上のサルの輸出を許可した契約をキャンセルした。
八一年三月二十六日付の『ウォール・ストリート・ジャーナル』によれば、ダッカのアメリカ大使館は、バングラデシユ政府に、輸出が再開されない場合は、アメリカからの政府援助を打ち切るとの脅迫まがいの圧力までかけていたという。
さらに、アメリカ大使館にこの輸出再開要求をゴリ押しさせたのは、契約をキャンセルされた動物業者だったとも伝えている。
この件のもっとも強硬なロビイストの一人は、WHOの生化学薬剤部長フランク・パーキンズ博士である。
博士の娘、ジェイ・パーキンズ・イングラムは、アメリカでジャッカス霊長類商会なるサルの輸入業を営んでいる。
***
インドの切実な外貨獲得の必要にもめげず、あえてアカゲザル輸出禁止に踏み切った当時のインド首相はモラルジ・デサイである。
七八年六月二日、ニューヨークでの記者会見での彼の発言は、アメリカ人報道関係者にとっては、人間性、倫理観、医学観などに関する耳の痛い教訓だった。
質問――首相御自身、我々人間にとっての医学上の必要性についてはよく御理解いただいているとは思いますが、研究用アカゲザル輸出反対の立場を御説明頂けますでしょうか。
答――真の人間であるならば、いかなる生きものに対しても残酷な仕打ちはすべきではない、というのがインドの哲学です。
それゆえに我々はいかなる動物も人間による残虐行為の対象となるべきではないと考え、輸出を拒否しているのです。
現在のような科学研究だけが人類の幸福への答ではありません。
自然の法則に従うことにより、人類は幸福、健康へとより大きく前進できるでしょう。
この方法では薬はまったく不要です。
私自身、これまで何年も、そして現在も、薬は使っていません。
***
動物実験業界およびいわゆる保健機関により暗黙のうちに公認されているごく日常的な実験を少し紹介してみよう。
〔イルカの自殺〕イルカの知能はひょっとすると人間以上かもしれないとさえ言われるが、実験によるフラストレーションと不安に耐えかねて、実際に自殺をするイルカもいると言われている。
〔苦痛を与えられて殺されている動物の数〕アメリカだけでも年間九〇〇〇万匹近くに上る。
そのうち三四〇〇万匹が製薬業界の犠牲である。
動物だけではない、何万人という人間までもが、製薬会社の間違いだらけのしかも言いわけにしか役に立たない実験の犠牲になっている。
〔イギリス、ハンティントン研究所での実験〕ウサギの目にシャンプー液を噴きつけると、その激しい痛みに耐えかねて普段は声を出さないウサギでさえ叫び声を上げるという(この種のテストを行なったことを認めている企業は、レブロン、ウェラ、エリザベス・アーデン、ファベルジェ、ジレット、コティ、モンテイル、ヘレナ・ルビンスタイン、ジョンソンなど。
ヤードレイは数年前に動物使用を中止したと語っている)。
〔痛みの効果を調べる実験〕イヌやネコを熱した鉄板の上におくと、踊り狂い、灼けた手足を吹いてさまそうとする。
〔有害食物実験〕無理矢理、有害食物を食べさせられたビーグル犬は、何日も苦しんだ揚句死んだが、その血液はチョコレート色に変色していた。
〔固定実験〕さまざまな種類の動物が拘束衣その他の固定装置によってまったく動けないようにされた結果、完全に麻痺したり発狂したりした。
固定装置にくくりつけたサルたちに定期的に電気ショックを与え続けたところ、胃の腫瘍で次々と死んだ。
最後の一匹が死んだのは実験開始二三日目だった。
〔歯痛と食物〕イヌの歯の根幹にドリルで穴を開け、イヌが食物を食べる時の痛みをいかにしてコントロールするかを調べた。
〔暗闇実験〕仔ネコの両眼を縫いつけ、暗闇の中でどのような反応を示すかを調べた。
この種の実験はこれまであちこちの国で際限なく繰り返されている。
〔ラットが溺れるまで〕ラットを水の入ったタンクに落とし、溺れるまでにとのくらいかかるかを調べた。
すぐに「絶望して」溺れ死ぬラットもいれば、六〇時間も頑張って泳ぎ続け、力尽きて死ぬラットもいるという。
〔不眠の影響を調べる実験〕実験動物をノーブル=コリップ・ドラム(noble-Collip drums)に入れて上下に激しく振り回し眠らせないようにすると、三〇日間も寝ずに耐え、ようやく死ぬ動物もあった。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
イギリスの女医第一号、アナ・キングスフォード博士は次のように書いている。
「動物実験者の魂に巣食う精神の堕落は、彼から最高最善の知識を得る能力を奪う。
彼は健康の秘密を発見するよりは、病気を蔓延させることの方がはるかに容易だということを知るだろう。
彼は生命を蝕む細菌を探し求めるが、見出すのはただ新しい死に方のみである」。
***
科学は人類に迷信からの救済を約束した。
しかし、自らが歴史上、もっとも高慢で残虐な迷信と化した。
これは現代文明の生んだ最大の悲劇と言えよう――かつて、もっとも秀れた常識のフォルムであった科学は、今や神として生まれ変わった。
民衆(信徒)も科学者(司祭)とともに天上の声を聴く科学はかく仰せられる、かく求めておられる、と。
科学は機械的な神である――かつての神々は司祭に去勢を求めた。
しかし科学は司祭に、人間的感情を取り除くよう要求する(ブリジツド・ブロフイ『ザ・リスナ~』一九六九年)。
***
人の寿命は少しも変わっていない。
人は老いると病気がちになる。
どんなに多量の薬を飲もうと、どんな手当をしようと、六五歳という平均寿命は、この一世紀の間ほとんど変化していない。
薬は老化に伴う疫病には手の出しようがない。
老化現象そのものにはさらに手の出しようがない。
薬は
心臓病も癌も関節炎も肝硬変も、そしてごく普通の感冒さえも治せない。
確かに老いた人々の苦痛の一部は緩和できるようになった。
しかし残念ながら、一般論としては、老人への専門的医療措置は苦痛を増加させる。
そればかりでなく、措置がうまくいった場合、かえって苦痛を長引かせる結果になっている(イヴァン・イリッチ『医学のネメシス』p45,"ロンドン、一九七五年)。
***
「多数の労働者に職がない時、失業問題がおこる」というフーバー大統領の有名な論法がある。
実はこれは、学術論文でしばしば見かける論法なのである。
「生体が食物を与えられなければ飢餓がおこる我々はこれを、統計的に有意な数のイヌ、ネコ、サル、ロバ、ブタその他の動物を使って科学的に証明した。
また助成金が与えられれば、これを再度証明する準備がある」
しかし今日、「基礎研究」と呼ばれる仕事に携わる人々は、このような見え透いた言いわけをするだけの良心もなくしてしまったようだ。
「基礎研究」といえば響きは良いが、つまりは、健康な動物にまったく不必要な拷問を加え、肉体的精神的に破壊してしまうという作業のことである。
これは正気な人間にとっては、考えることさえ不可能、ましてや実行することなど論外な行為なのである。
↑
●動物たちの復讐『罪なきものの虐殺』への追補
WHOによれば、肉体的精神的にハンディキャップを負った人の数は、一九八〇年に世界中で四億五〇〇〇万人、すなわち世界人口の約一〇パーセントに上るという。
そのうち一億三六〇〇万人が一五歳以下である。
これは、健康環境が悪化し、かつてないほどに多くの子供たちが、国際教育財団のお節介で、いやがおうでも有害な医療介入を受けている結果の数字と言えよう。
たとえば、胎児期に母胎に施された治療、出生後の各種の予防接種、放射線、合成ビタミンや合成薬品の投与などである。
一億三六〇〇万人の内訳はヨーロッパ一一〇〇万、北米六〇〇万、ラテンアメリカ一三〇〇万、アフリカ一八〇〇万、アジア八八〇〇万となっている。
***
次に引用するのは『臨床薬理学および治療学』(Vol.7,1966,pp.250-270)に載ったイギリスのロバート・シャープ博士の、非常に啓蒙的な論文である。
これは、拙著『罪なきものの虐殺』の内容を確認するものである。
――フレミングはペニシリンが(ペニシリンは偶然に発見された。
動物実験によるものではない――著者)、血液によって不活性化するのではないかと考えていた。
この懸念は、サンプルをウサギに注射したところ、確認されたかのように思われた。
この結果に落胆したフレミングは、ペニシリンをさらに広汎に応用してみようという興味を失い、体表面の感染症に限って使用した。
後にオクスフォードのフローレイとチェインの二人がペニシリンに再注目し、ネズミで感染症に効果があることを確認した。
しかし、ここで幸運だったのが、実験動物の種類の選択である(二人がこの実験を開始した時、彼らの実験室では、もっとも一般的な実験動物であるモルモットが全部死んでいたのである――著者)。
ペニシリンはたとえ微量であってもモルモットには致命的である。
もしネズミの代わりにモルモットが実験に使われていたとすれば、おそらくペニシリンは永遠に日の目を見ることがなかっただろう。
さらに幸運が重なる。
ある重病の患者を救うためにフレミングはペニシリンを脊椎に注射することを考えた。
しかしその結果がどうなるかについては未知である。
フローレイは急ぎネコを使って実験を行なった。
が、その結果を待っていたのでは、フレミングの患者が助かるチャンスはなくなる。
ネコの結果が出る前に、患者はペニシリン注射を受け、回復した。
しかしフローレイのネコの方は死んだ。
この教訓は今もって生かされていないのである。
***
一九八一年四月二十三日、医師、研究者、作家、芸術家などからなる三〇名のイギリス人が、マーガレット・サッチャー首相宛ての嘆願書にサインした。
国の医学研究予算の一部を、動物実験に代わる別の方法の開発専用に回して欲しいという主旨のものだった。
この時も、それまでと同様、サッチャー首相は断固、冷たくNOと言い放った。
同年五月十四日付、ダウニング・ストリートからの返信は次のようなものだった。
「――生化学研究における動物使用に代わる研究方法開発のためにさける国家予算は、残念ながら、ありません。
医学研究委員会は、代替法に関する研究プロジェクトは、従来の研究プログラムの一環として行なうのがベストであると考えています――」。
この「医学研究委員会」なるものが強硬な実験主義者によって構成されているという点はここで指摘するまでもなかろう。
また、「科学畑」出身で、これまでも常に動物実験支持の姿勢を見せていたサッチャー首相は、自身がかつて動物実験に関わっていたのではないかという疑惑を持たれるのである。
事実、動物実験を認めるほどの人は誰でも、実験そのものへの参加をも躊躇しないだろう。
***
西ドイツの保健相アンジ・ヒューヴァーの姿勢もサッチャー首相のそれに非常によく似ている。
一九八一年六月二十五日、ヒューヴァー保健相はボンでの公聴会の席上、動物実験を破棄することはできないし、部分的廃止たとえば化粧品のための実験や残酷な上に間違った結果を導きがちなLD-50(対象動物の五〇パーセントに対する致死量)テストなど――も問題外である、ときっばり言い切った。
ちょうどその頃、保健相の同僚ミルドレッド・シールが、「癌征服プログラム」
のために、マルクをかき集めている最中だった。
ヒューヴァー保健相は、他の仕事があるからと言い二〇分で公聴会から逃げ出した。
あとは保健省の役人の一人が引き継いだ。
この役人は、実験削減の実施すらも難しいと述べた。
というのは、保健省が実験の実態を完全に把握しきれていないためだという。
「たとえば、我々は我が国の大学の中で、何がおこっているのか知りません」と彼女は言う。
また、なぜ保健省がせめて悪評フンプンのLD-50テストだけでも禁止しないのか、と聞かれて、こう答えている。
「もしそんなことをすれば、我が国は薬品を輸出できなくなります」。
この時、彼女は明らかに、アメリカの時代遅れのディレイニイ改正法に言及していたのである。
この改正法は、各種のテストを義務づけたもので、今日の全世界の薬害に大いに責任を負うべき法律なのである。
また、彼女の回答は、サッチャー首相、ヒューヴァー保健相をはじめとする先進工業国の政治家たちが、製薬トラストの利益にいかに深く絡んでいるかを示す証言だったのである。
***
ニューヨーク州ローゼスポイントで発行されているタブロイド誌『ザ・グローブ』の一九八〇年五月二十七日付の記事に次のようなものがあった。
空軍の極秘化学戦・レーザー線研究に携わっていた心理学者が明らかにしたところによれば、殺人光線や電気ショックによってアカゲザルが情容赦なく盲目にされたり苦痛を与えられたりしているという。
テキサス州サン・アントニオのブルクス空軍基地での実験に使われたアカゲザルは、その傷めつけられ方があまりにもひどかったため、自己破壊的になり、自分の腕の肉を噛みちぎったり、胸から毛の塊を抜き取ったりするようになった、と心理学者のドナルド・バーンズは『ザ・グローブ』の単独インタビューに答えて語った。
バーンズはオハイオ州立大学の卒業生で、ブルクス空軍基地で一六年間、研究者として非の打ちどころのない仕事ぶりだった。
しかし、実験用サルの扱いが余りにもひどいため、これを世間に公表すると抗議したところ、今年一月に解雇されたという。
空軍スポークスマン、サルバトーレ・ギアンモは、空軍施設は、実験動物認定協会の検査官による立入検査を、一九七九年五月十五日に受けており、その際、問題なしと判定されたと語っている。
しかし、たとえば首の回りの拘束カラーがきつすぎたため、窒息死した三匹のサルを目撃したとバーンズは語る。
さらにこう証言する。
「椅子に縛りつけられたサルたちが、胸の前でクロスしている金属の棒の間から死にもの狂いで抜け出そうともがいているのも見ました。
サルたちが余りにも激しくもがくので金属棒が腹壁に食い込み始めていました」。
アカゲザルが実験動物として重宝されるのは、穏やかで非常に信頼のおける動物だからである……。
バーンズは言う。
「――台はユラユラ揺れるようになっており、我々はサルたちにその台をまっすぐにするレバーの使い方を教えました。
その訓練の仕方というのは、足の裏に金属板をつけ、
彼らが迅速に正確にレバー操作をしないと、そこに電流が流れるようになっているのです。
なかなか操作を覚えないサルには、突然電気を流してショックを与えて罰しました。
サルは一日に何百回もショックにつぐショックを与えられます――けれども私たちの行なっていた実験はほとんど無意味なものでした。
すでに以前、行なわれたことのある実験ばかりだったんです」。
***
一九七九年九月二十四日付、ロンドンの日刊紙『スター』より。
実験施設へ送られるサルたちは、檻にぎっしり詰め込まれたままの状態で激しく鳴き叫ぶ。
そのため喉が膨れ上がり呼吸ができなくなる。
インドネシアから発送された六二五匹のうち、恐怖の空の旅を耐え抜いて、生きてスウェーデンに着いたのはたった一四〇匹だけだった……。
アムステルダム空港で、サルの輸送風景を目撃したディック・ヴァン・ホーンのコメント。
「九月八日、インドネシア、ジャカルタからスウェーデン、ストックホルムへ送られる数百匹のサル(ジャワ産、アカゲザル)が、乗りつぎのため、アムステルダム空港で数時間待たされていた――取り締まり官が檻のうちふたつを開けるよう命じた。
ひとつの檻には一五匹のアカゲザルが入っていたが、そのほとんどすべてが怪我をしていた。
もうひとつの檻には一一匹いたが、そのうち七匹はすでに死んでいた。
これらのサルの死因は明らかに空気不足で、眼球はとび出し、舌は自分で噛みちぎったものらしかった。
取り締まり官は灯りをかかげて、他の檻も検査したが、次々に死んだサル、怪我をしたサルが発見された――」。
***
国際霊長類保護協会(IPPL)の会長、シャーリー・マクグリ~ル博士のリポートから、サルの輸出に関する情報を少し拾ってみよう。
インド政府は一九七七年、サルが残酷な放射能実験に使われていることに抗議して、輸出禁止に踏み切った。
アメリカとWHOからの強力な圧力、またインド自身の政権交替にもかかわらず、現在も、輸出は再開されていない。
バングラデシュ政府は一九七九年、あるアメリカの業者に七万匹以上のサルの輸出を許可した契約をキャンセルした。
八一年三月二十六日付の『ウォール・ストリート・ジャーナル』によれば、ダッカのアメリカ大使館は、バングラデシユ政府に、輸出が再開されない場合は、アメリカからの政府援助を打ち切るとの脅迫まがいの圧力までかけていたという。
さらに、アメリカ大使館にこの輸出再開要求をゴリ押しさせたのは、契約をキャンセルされた動物業者だったとも伝えている。
この件のもっとも強硬なロビイストの一人は、WHOの生化学薬剤部長フランク・パーキンズ博士である。
博士の娘、ジェイ・パーキンズ・イングラムは、アメリカでジャッカス霊長類商会なるサルの輸入業を営んでいる。
***
インドの切実な外貨獲得の必要にもめげず、あえてアカゲザル輸出禁止に踏み切った当時のインド首相はモラルジ・デサイである。
七八年六月二日、ニューヨークでの記者会見での彼の発言は、アメリカ人報道関係者にとっては、人間性、倫理観、医学観などに関する耳の痛い教訓だった。
質問――首相御自身、我々人間にとっての医学上の必要性についてはよく御理解いただいているとは思いますが、研究用アカゲザル輸出反対の立場を御説明頂けますでしょうか。
答――真の人間であるならば、いかなる生きものに対しても残酷な仕打ちはすべきではない、というのがインドの哲学です。
それゆえに我々はいかなる動物も人間による残虐行為の対象となるべきではないと考え、輸出を拒否しているのです。
現在のような科学研究だけが人類の幸福への答ではありません。
自然の法則に従うことにより、人類は幸福、健康へとより大きく前進できるでしょう。
この方法では薬はまったく不要です。
私自身、これまで何年も、そして現在も、薬は使っていません。
***
動物実験業界およびいわゆる保健機関により暗黙のうちに公認されているごく日常的な実験を少し紹介してみよう。
〔イルカの自殺〕イルカの知能はひょっとすると人間以上かもしれないとさえ言われるが、実験によるフラストレーションと不安に耐えかねて、実際に自殺をするイルカもいると言われている。
〔苦痛を与えられて殺されている動物の数〕アメリカだけでも年間九〇〇〇万匹近くに上る。
そのうち三四〇〇万匹が製薬業界の犠牲である。
動物だけではない、何万人という人間までもが、製薬会社の間違いだらけのしかも言いわけにしか役に立たない実験の犠牲になっている。
〔イギリス、ハンティントン研究所での実験〕ウサギの目にシャンプー液を噴きつけると、その激しい痛みに耐えかねて普段は声を出さないウサギでさえ叫び声を上げるという(この種のテストを行なったことを認めている企業は、レブロン、ウェラ、エリザベス・アーデン、ファベルジェ、ジレット、コティ、モンテイル、ヘレナ・ルビンスタイン、ジョンソンなど。
ヤードレイは数年前に動物使用を中止したと語っている)。
〔痛みの効果を調べる実験〕イヌやネコを熱した鉄板の上におくと、踊り狂い、灼けた手足を吹いてさまそうとする。
〔有害食物実験〕無理矢理、有害食物を食べさせられたビーグル犬は、何日も苦しんだ揚句死んだが、その血液はチョコレート色に変色していた。
〔固定実験〕さまざまな種類の動物が拘束衣その他の固定装置によってまったく動けないようにされた結果、完全に麻痺したり発狂したりした。
固定装置にくくりつけたサルたちに定期的に電気ショックを与え続けたところ、胃の腫瘍で次々と死んだ。
最後の一匹が死んだのは実験開始二三日目だった。
〔歯痛と食物〕イヌの歯の根幹にドリルで穴を開け、イヌが食物を食べる時の痛みをいかにしてコントロールするかを調べた。
〔暗闇実験〕仔ネコの両眼を縫いつけ、暗闇の中でどのような反応を示すかを調べた。
この種の実験はこれまであちこちの国で際限なく繰り返されている。
〔ラットが溺れるまで〕ラットを水の入ったタンクに落とし、溺れるまでにとのくらいかかるかを調べた。
すぐに「絶望して」溺れ死ぬラットもいれば、六〇時間も頑張って泳ぎ続け、力尽きて死ぬラットもいるという。
〔不眠の影響を調べる実験〕実験動物をノーブル=コリップ・ドラム(noble-Collip drums)に入れて上下に激しく振り回し眠らせないようにすると、三〇日間も寝ずに耐え、ようやく死ぬ動物もあった。